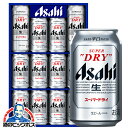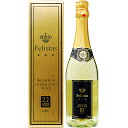こんにちわ、
よしおです。
キリストの生まれた場所は、ヨルダン川西岸にあるベツレヘムと言われています。
つまり砂漠地帯なのですが、それとクリスマスの主役である、サンタ・クロースの格好とモミの木、トナカイといい北極圏の動植物が登場するのがどうもしっくりいきません。
ということで調べてみると、なるほど、つまりクリスマスというのは、資本主義が生んだ、虚構だということがわかります。
でも、うそもつき通せば、そのうち信用されるのと同じで、習慣として定着してしまったものと思います。
スポンサーリンク
クリスマス サンタクロースの起源と正体
クリスマスの主役であるサンタクロースの起源をたずねれば、この人物は四世紀のころ、小アジアのリシアにいたミラ大僧正セント・ニコラウスのことです。
小アジアは現在のトルコの場所です。
しかもセント・ニコラウスというのは、盗賊、強盗の守護神でした。
こんにちでも、南欧、東欧などでは、スリのことを「セント・ニコラウスの騎士」と呼びます。

※トルコ・イスタンブール
また、中世以来、地中海や大西洋であばれまわった海賊たちも、海賊旗のしるしにセント・ニコラウスの肖像をあしらっていました。
これが西欧、北欧では、どういうわけか子どもを守る神様、というふうに変形するんですね。この辺がよくわかりません。
スポンサーリンク
ドイツでは12月6日に贈り物をもらうらしい
ドイツでは、12月6日が聖ニコラウスの日にあたり、この日にはサンタさんが、ふだん善行の多い子どもには贈物を、そして行いのよくない子には木の枝を持って訪れる、ということになっています。
むしろこの日が本当のクリスマスで、25日にもう一つのクリスマスということです。
ドイツでは5日の夜に、靴を綺麗に磨いてから、または大きな靴下を用意してから眠りにつくのが習わしになっています。
ドイツの”定番のクリスマスを感じられるもの”は、チョコレート、オレンジ、紅茶、シナモン、クルミなどです。

その聖ニコラウスの日がクリスマスと融合して、12月24日にいつのまにやら移動したのでしょう。
いや移動した言うより二分されたと行ったほうが良いのでしょうか。
クリスマス行事は、融合と妥協の産物
だいたい、クリスマス行事というのは融合・妥協の産物であって、この日がキリスト生誕の日である、という証拠はどこにもありません。
実際、キリスト生誕の日は聖書にも記載がなく、二世紀ごろまでは5月10日に聖誕祭が行われていました。
12月25日がクリスマスになったのは、キリスト教がゲルマン社会に入って、冬至祭と結合してからのちのことです。

ほんらい砂漠地帯で生まれたはずのキリストが、雪のちらつくところを舞台に、しかも、モミの木だのトナカイだのといった北極圏の動植物とともにその生誕を祝われる、というのはふしぎな風景です。
最後に
クリスマス・プレゼントなるものがひろくおこなわれるようになったのは、1920年代以降です。
いまから100年ほど前ですね。

アメリカの百貨店資本が、すさまじい宣伝活動をはじめててから以降のことです。
クリスマス サンタクロースの起源から
 10,500円(税込)【送料込】
10,500円(税込)【送料込】
茨城県守谷市
3年連続ノンアルコールビール売上No.1!!!最もビールに近い味のノンアルコールビール『アサヒ ドライゼロ』350ml 1ケース 24本。ドライなのどごしとクリーミーな泡のビールらしい飲みごたえで食事にも合うすっきりした味わい。『カロリーゼロ・糖質ゼロ』のアサヒのノンアルコールビ
 11,500円(税込)【送料別】
11,500円(税込)【送料別】
ウメムラ Wine Cellar
※写真2の様に、クリスマス仕様のミュズレが別梱包になっているものと、キャップシール内に装着されているものが混在しております。どちらかをご指定いただくことはできません。ご承知の上、お買い求めください。 数量限定! 大人気シャンパーニュ「ルプルー・プネ」より 特別にクリスマスにピッタ
 7,920円(税込)【送料別】
7,920円(税込)【送料別】
ウメムラ Wine Cellar
ホリデー気分を盛り上げてくれるクリスマス仕様のボトルのブラン・ド・ノワール! シャンパーニュ シャルル・ド・カザノーヴは1811年、シャンパーニュの銘醸地コート・ド・ブランのアヴィーズの地に設立されました。ヨーロッパ諸国の王侯貴族や政治家に好まれ、特にイギリスのエドワード7世は、
 3,520円(税込)【送料別】
3,520円(税込)【送料別】
ボックスワインのお手軽ワイン館
ギフト対応 幸せのおまじない『サムシング・ブルー』 青いスパークリングワインにあなたの想いをこめて・・・ ★大人気!累計8,520本完売! (2023年8月末現在) エルヴェ・ケルランは、「手頃な高級品」をコンセプトに、 コスト・パフォーマンスに優れたワインを生み出す生産者。 透
 792円(税込)【送料別】
792円(税込)【送料別】
ベルギービールJapan
テットゥ・ド・モール クリスマス330mlの解説 テットゥ・ド・モール・X-MASは、「テットゥ・ド・モール」シリーズの新しいビールで、2022年に誕生しました。姉妹品と同様、アルコール度数が8.1%と高いフルボディタイプのビールです。ラベルに描かれた骸骨には、お祝
 3,980円(税込)【送料別】
3,980円(税込)【送料別】
Regaloレガーロセレクトギフト
※商品詳細につきましては、画像にてご案内しております。 ご確認くださいませ。 ※北海道・沖縄県・離島は別途送料がかかります。 予めご了承くださいませ。 ※ボトルでの発送となるため、ラッピングやお熨斗には対応しておりません。 予めご了承くださいませ。
![クリスマス ツリー型 ボトル ワイン ロゼ 500ml[常温/冷蔵可]【3〜4営](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cerestshop/cabinet/beverage/beverage6/333922-195.jpg?_ex=128x128) 2,180円(税込)【送料別】
2,180円(税込)【送料別】
セレスト(cerest)
<< ITEM INFORMATION >> 名称(原語) SMW Christmas Bottle Wine RoseSMW クリスマス ボトル ワイン ロゼ 商品詳細 季節限定のクリスマスツリー型ボトルのワインです。ちょっとしたプレゼントにも喜ばれるツリー型の可愛らしいデザイ
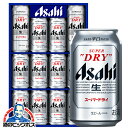 2,954円(税込)【送料別】
2,954円(税込)【送料別】
酒のビッグボス
■北海道・九州・四国の配送はプラス300円かかります。 ■離島・沖縄への配送には別途送料がかかります。 【ご注意ください】 ご注文確定後の のし変更、依頼主変更、キャンセルなど 後からの変更依頼は 発送準備にかかっている為 出来ません。 内容がお間違えない事をご確認の上、 注文確
 6,600円(税込)【送料別】
6,600円(税込)【送料別】
ココロを贈る 名入れギフトOkulu
サイズ 容量750ml 素材 ガラス 原産国 ドイツ Felistas (フェリスタス) ■原産国 : ドイツ ■タイプ : やや辛口 ■種類 : スパークリングワイン (白) ■アルコール分 : 11度 ■ブドウ品種 : リースリング、ミュラートゥルガウ 備考 改良のため、予
 7,678円(税込)【送料込】
7,678円(税込)【送料込】
うきうきワインの玉手箱
■さまざまなギフトアイテムをご用意しております。お中元 ギフト 御中元 お盆 お礼 敬老の日 クリスマス 冬ギフト お歳暮 御歳暮 お年賀 御年賀 お正月 年末年始 ご挨拶 バレンタイン ホワイトデー お返し 父の日 母の日 ギフト 贈答品 お土産 手土産 御祝 御礼 内祝い 引
 1,960円(税込)【送料別】
1,960円(税込)【送料別】
リカオー
MOSEL SPATBURGUNDER ROSE毎年、完全受注生産で発売される、クリスマスツリー型のボトルに入ったワインです。可愛いボトルが毎年大人気です!--------------------------------------------------------------
 1,695円(税込)【送料別】
1,695円(税込)【送料別】
うきうきワインの玉手箱
年代 造り手 ー ロジャーグラート(アグロリメン社) 生産国 地域 スペイン バルセロナ 村 タイプ ロゼ・スパークリング・辛口 内容量 750ml ■さまざまなギフトアイテムをご用意しております。お中元 ギフト 御中元 お盆 お礼 敬老の日 クリスマス 冬ギフト お歳暮 御歳暮
 1,199円(税込)【送料別】
1,199円(税込)【送料別】
うきうきワインの玉手箱
1984年に英国で始まり、以後毎年同国で開催されている世界最大規模の国際ワインコンクールが、1998年、1999年、2000年に日本でも「ジャパン・インターナショナル・ワインチャレンジ」として開催されました。例年1200〜1600銘柄のチャレンジがあり、その規模は、アジア最大。
 7,678円(税込)【送料別】
7,678円(税込)【送料別】
リカーショップたかはしweb
商品名正規品 ピスコ ポルトン 750ml箱入 ・アチョラード 2024年クリスマス限定デザイン ・アチョラード ・アチョラード マチュピチュ エディション ・アルビージャ ・イタリア ・ケブランタ ・トロンテル ・ネグラクリオージャ ・モジャール総本数1本アルコール度数43%販
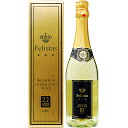 2,420円(税込)【送料別】
2,420円(税込)【送料別】
酒類の総合専門店 フェリシティー
ITEM INFORMATION 22カラットの金箔が入った ”幸福”を運んでくる辛口スパークリング FELISTAS PREMIUM SPARKILING フェリスタス プレミアム スパークリング ワイン 「フェリスタス 金箔入りスパークリングワイン」は、ラテン語で「幸福」とい
スポンサーリンク











![クリスマス ツリー型 ボトル ワイン ロゼ 500ml[常温/冷蔵可]【3〜4営](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cerestshop/cabinet/beverage/beverage6/333922-195.jpg?_ex=128x128)